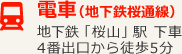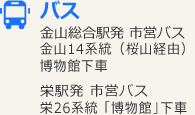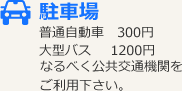-
彭城百川の絵文字
彭城百川の絵文字 ユニークな俳書デザイン
彭城百川(さかきひゃくせん、1697~1752)は、江戸時代の中ごろに活動した名古屋出身の文人画家である。「文人画(ぶんじんが)」とは、文人(知識人)が自らの学識を活かし余技として描くという中国絵画の理想を反映した絵画ジャンルである。百川は、最新の絵画動向であった文人画の旗手として、本場中国の作品や絵画教本を参考に、独自の画境を切り開いた。一方、早年の頃から俳諧(はいかい)にも親しみ、清新な内容の句をはじめ、俳書(はいしょ)の挿絵やデザインにも目立った業績を残した。本稿では、百川の俳書デザインの内、絵文字を中心に取りあげ、その出典を推測する。さらに、百川が中国風の作品を手がける文人画家として飛躍していく背景に、当地の俳壇における中国趣味を想定したい。
美濃派の俳書デザインと絵文字
後に専業の画家となるが、元々百川は名古屋城下本町一丁目東側にある薬屋の主人であった(入婿であったと推測される)。20代の頃から城下の旦那衆たちと俳諧に遊んでいたようだ。やがて松尾芭蕉(まつおばしょう、1644~94)の弟子である各務支考(かがみしこう、1665~1731)に就き、俳諧に熱を上げていく。美濃に門戸を張った支考は、名古屋をはじめ各地に勢力を拡大し多くの門人たちを抱えていた。彼らは総称して「美濃派(みのは)」と呼ばれるが、その美濃派の俳書や、美濃派とも縁の深い名古屋の宗匠(そうしょう)たちの俳書に見る装飾の一つに、絵文字がある。植物や霊獣、宝玉といった具象物が寄り集まって文字(漢字)を構成する。双龍文(そうりゅうもん)や植物文とあわせて扉(とびら)の内題(ないだい)等に用いられることが多かった。30歳になった百川が、初めて自ら編んだ俳書『本朝八仙集(ほんちょうはっせんしゅう)』(享保11年〈1726〉跋)において大々的に採用されていることから、多くの絵文字は百川の筆にかかるものと推測されている。
『歴朝聖賢篆書百体千文』の雑体書
ここでは絵文字の実例を其麦 編『七化集(ななばけしゅう)』(宝暦2年〈1752〉刊)に見てみよう。四季にわたる七つの題を詠んだ内容に合わせて、「春夏秋冬」の絵文字が冒頭に掲げられている(図1)。撰者である其麦(きばく)は、名古屋の俳人・武藤巴雀(むとうはじゃく、1686~1752)の高弟である。巴雀と支考および百川は、俳席を共にするなど深い交流があった。本書が出版された時分、百川は生業と家庭を捨て去り、京都を拠点に文人画家として大作を手がけていたが、旧縁によって挿図を提供することになったのであろう。絵文字を構成するモティーフの密度や整ったバランスを鑑みても、『本朝八仙集』の絵文字に比肩する出来栄えである。

図1 其麦 編『七化集』部分 館蔵
こうした絵文字の出典として考えられる字書が、中国で出版された孫枝秀 編『歴朝聖賢篆書百体千文(れきちょうせいけんてんしょひゃくたいせんもん)』(康熙24年〈1685〉序)である(図2)。

図2 孫枝秀 編『歴朝聖賢篆書百体千文』 名古屋市蓬左文庫蔵
漢字の基本学習に用いる千字文(せんじもん)を8字ずつ、125体の書体で書き分けて収録する。それぞれの書体は、絵文字と呼ぶべき意匠化されたものが多く、古代に遡る歴史や由来等が付記されている。書体の一例である「八宝文」を取り上げよう(図3)。三国時代の能書家として名高い韋誕(いたん、181~253)が、古い天子の陵から出土した宝玉や銭貨をかたどって、この文字を編み出したという。珊瑚や銭貨、如意(にょい)、丁子(ちょうじ)などで構成される姿は、『七化集』題字「春夏秋冬」の内、「夏」の絵文字とよく似ていることが分かる(図4)。他の絵文字の書体も、概ね同書に基づくらしい。百川は、「雑体書(ざったいしょ)」と呼ばれる漢字の様々な書体に、造形美と遊び心を見出し、俳書を彩る装飾的要素の一つとして応用したのではないだろうか。

図3 『歴朝聖賢篆書百体千文』「八宝文」のうち「尋」字

図4 『七化集』題字「春夏秋冬」のうち「夏」字
『歴朝聖賢篆書百体千文』が載せるような雑体の篆書は、唐様の書家を中心に受容され、法帖や字書等において使用されていることが指摘される。また篆刻印の印文や縁起物の掛幅等にも転用されていくようだ。『歴朝聖賢篆書百体千文』自体、早くも正徳年間(1711~16)には和刻本が出版されており、寺島良安 編『和漢三才図会』(正徳3年〈1713〉序)巻15にも「歴代文字」として数文字が引用されている。百川の目に触れる機会は十分にあっただろう。
俳人から文人画家へ
美濃派をはじめとする当時の俳人たちは、中国の字書に収録された書体に興味を持ち、中国的な意匠で俳書を飾るなど、中国趣味を共有していたことが想定される。同じく支考と関係の深い名古屋の俳人・太田巴静(おおたはじょう、1678~1744)による春興帖『廿日正月(はつかしょうがつ)』(享保16年〈1731〉刊か)も、濃厚な中国趣味を感じさせる俳書である(図5)。団扇形(だんせんけい)の梅図に絵文字風の書題「廿日正月」を配した瀟洒な題簽(だいせん)が印象的だ。百川が本格的な文人画を手がけるようになったのは、名古屋を離れ、京都にて活動するようになった頃からと思われる。しかしながら、文人画をはじめとする中国文化への興味は、名古屋時代の俳壇における活動や交流のなかで醸成されたものと推測される。漢詩文を読みこなし、換骨奪胎して当世風に詠み替える俳人たちが、中国の文物に関心を持つことは当然の成り行きであろう。日本文人画の先駆者が俳人であったことは、単なる偶然では無いのである。

図5 太田巴静 編『廿日正月』 館蔵
(横尾拓真)
以上で紹介した諸資料は常設展示しておりません。あしからずご了承ください。
参考文献
清水孝之「彭城百川の俳諧―その前半生」『愛知県立芸術大学紀要』13、1983年3月
名古屋市博物館 編集・発行『知られざる南画家 百川』1984年3月
岩坪充雄「江戸時代の書物と雑体篆書」『書物・出版と社会変容』15、2013年10月